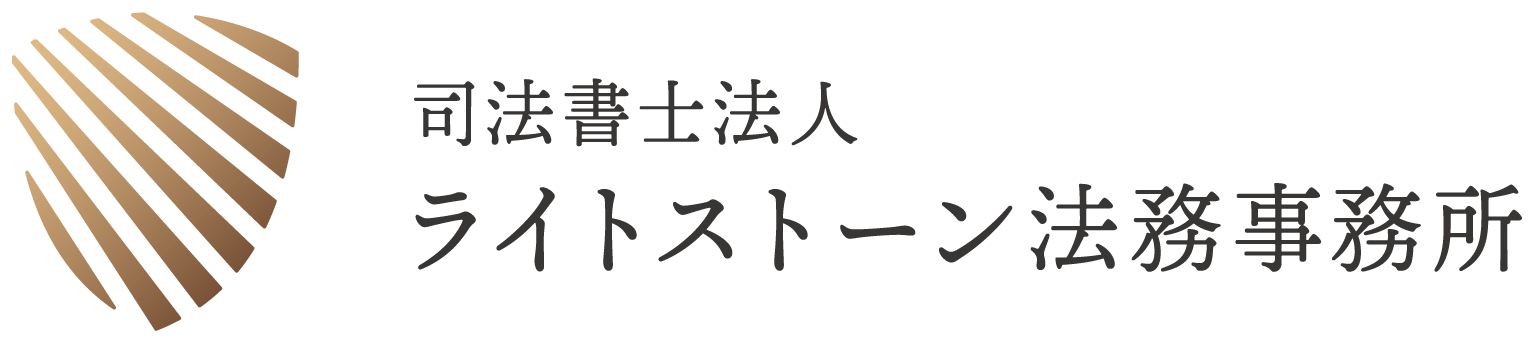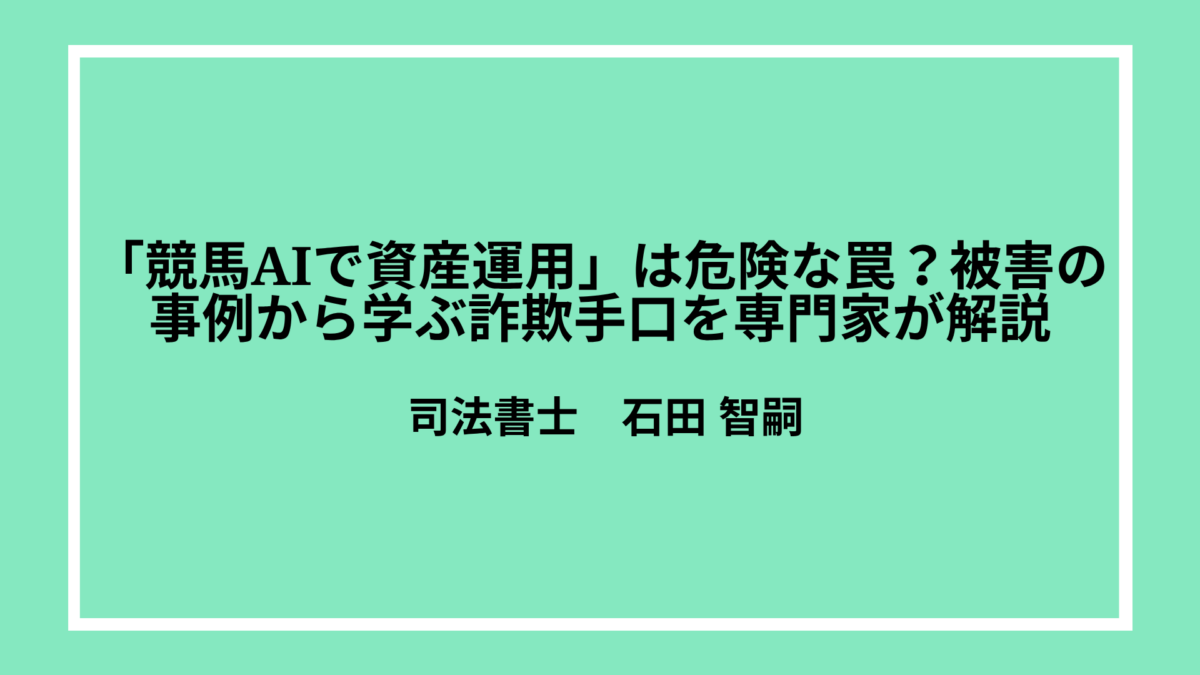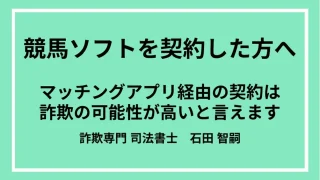「AIを使って、競馬をギャンブルから安定した資産運用へ」「専門知識は不要。AIの予測に従うだけで、資産が増えていく」
「競馬AIで資産運用」という新しい響きに、未来の可能性を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一方でこうしたAI使った競馬投資詐欺がSNSを利用して急増しております。
実際、警視庁のデータによると2023年の認知件数でSNS型投資詐欺が認知件数2,271件、被害額約277.9億円 (1件あたり平均約1,224万円)とあり、かなりの被害となっております。
この記事では、「競馬は資産運用になる」と信じてしまった結果、多額の金銭を失った方々のリアルな事例をもとに、その危険な手口について専門的見地からの分析と、万が一被害に遭ってしまった場合の解決策を解説します。
なお、競馬マッチングアプリソフトで詐欺被害の流れについて「マッチングアプリでの競馬投資ソフト契約は詐欺の可能性あり?詐欺手口と返金事例を徹底解説【2025年版】」を併せてご覧ください。

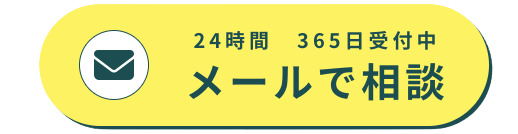
下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)
「AI競馬は資産運用」を信じた人々の被害実例と解説
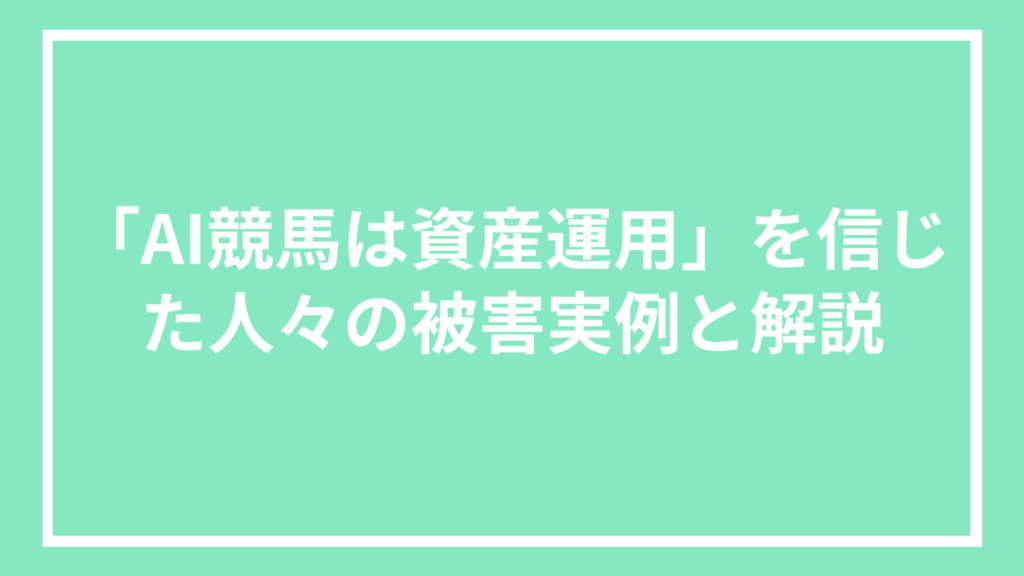
「競馬AI」や「競馬投資」を謳う詐欺の被害は、決して他人事ではありません。
ここでは、実際に被害に遭われライトストーン法務事務所にご相談があった3名の方のケースをご紹介します。
返金事例:20代・女性「被害・請求額59万円 ▶ 回収額36万円(約61%回収)」
副収入が欲しくて、副業サイトや稼いでいる方のSNSをフォローして調べていました。そんな時に、こういう女性になりたいと思えるような人をインスタで見つけたんです。稼いでいて、考え方も学ぶことが多くて「上手くいく人ってこんな感じなんだ」と尊敬したりして。
それでアカウントをフォローして、いろいろな投稿にいいねをしているうちにDMが来て、嬉しくて舞い上がりました。その後、話を聞くと「競馬で稼いでいる」と教えてくれて興味を持ちました。
「競馬はギャンブルではない」「情報があれば稼げる」という言葉を信じて、未来に投資したつもりで有料情報を購入したのですが、ぜんぜん稼げなくて、元気もなくなり困っていました。
私の様子を心配した友人に話をしたところ、騙されていることに気づかせてくれて、石田先生に対応をお願いをしました。今は返金されたこと、悩みの原因がなくなったことに安心しています。
この事例のからわかるように「AIマッチング競馬詐欺」は、計画的かつ段階的に進められます。
まず最初のステップとして、詐欺師はSNS上で経済的成功を収めた魅力的な人物像を演出し、ターゲットに「自分もこうなりたい」という強い憧れを抱かせます。実際、最初被害者は加害者側に尊敬の念を抱いておりました。
その後、親密なダイレクトメッセージのやり取りを通じて、単なる憧れの対象から「信頼できる指導者」へと巧みに立場を変え、ターゲットの警戒心を完全に無力化してしまうのです。
次に、相手が自分を信用しきったタイミングで、巧みな言葉のすり替えを行います。
本来「ギャンブル」である競馬を、あえて「投資」や「資産運用」と表現することで、リスクや後ろめたさを感じさせず、むしろ「未来のための賢明な活動」であるかのように錯覚させます。
これにより、高額な情報料を支払うことへの心理的なハードルを劇的に下げさせます。
そして最後の仕上げとして、その「投資」の根拠を権威付けします。
「AIによる高度な分析」「最適なマッチング」といった、科学的で客観的に聞こえる言葉を使い、情報の価値を不当に吊り上げます。
利用者はAIの性能やロジックを確かめようがないため、「すごいものらしい」という漠然とした信頼感から、不確かな情報に大金を支払ってしまうのです。
このように、最新技術を装ってはいますが、その本質は、人の憧れや権威への弱さといった心理的脆弱性につけ込む、昔ながらの詐欺の手口に他なりません。

「AIによる分析」といった科学的な権威を装い、利用者が検証できない情報を信じ込ませるのが特徴です。最新技術を謳いますが、本質は人の心理的弱点につけ込む古典的な詐欺手口です。
返金事例:30代・男性「被害・請求額110万円 ▶ 回収額40万円(約36%回収)」
副業を探している時に競馬予想サイトのことを知りました。競馬情報サイトに無料登録したのは、競馬に興味があったこと、副業で収入を増やしたいと思っていたことがあります。
ずっと競馬予想サイトを見ていると「自分でも稼げるのではないか」と思えてきて、どんどん賭けてしまいました。
負ければ負けるほど、取り返そうという気持ちが強くなって、気づいたら100万以上も使っていることに気づいてショックで。馬券代を入れるともっとです。
さすがに怪しいと思って調べていくと騙されているとわかって。泣き寝入りはしたくなかったので、お金を取り戻せて良かったです。
すべての始まりは、「自分でも稼げるのではないか」という期待感です。
競馬予想サイトを眺めているうちに、多くの成功事例に触れ、あたかも自分が状況をコントロールできるかのような錯覚、いわゆる「コントロールの幻想」に陥ります。
この根拠のない自信が、最初の一歩である有料情報の購入を踏み出させてしまうのです。
しかし、いざ始めて負けが込むと、事態は深刻化します。事例の核心である「負けを取り返したい」という強い衝動は、ギャンブル依存症にも見られる「チェイシング(追いかけ)」と呼ばれる危険な心理状態です。
損失を取り戻すために、さらに大きなリスク(より高額な情報料の支払い)を冒してしまう非合理的な行動で、詐欺師はまさに「次こそ勝てる」「この情報で取り返せる」と、この心理を巧みに煽ってきます。
そして、気づけば100万円以上をつぎ込んでしまった背景には、「サンクコスト効果」があります。
これまで支払った多額のお金を「もったいない」と感じるあまり、「今やめたら全てが無駄になる」と思い込み、損失が続くと分かっていながらも、合理的な撤退の判断ができなくなってしまうのです。
「怪しい」と感じながらもやめられなかったのは、この心理が強く働いていたからに他なりません。

この事例は単に騙されたという話ではなく、詐欺師によって人間の普遍的な認知の歪みが利用され、被害が雪だるま式に膨らんでいったケースと言えます。これは意志の強さの問題ではなく、誰もが陥る危険性をはらんだ心理的な罠なのです。
返金事例:20代・男性「被害・請求額60万円 ▶ 回収額45万円(約75%回収)」
副業を探している時に、インスタでお金を稼いでいる男性のアカウントをフォローしました。稼ぐための情報が欲しくて、興味を持ってしまったんですね。
インスタのフォロー後、間もなくDMをいただいたのですが、メッセージを繰り返すうちに「競馬初心者の自分でも稼げるかもしれない」と思ってしまったんです。
そこで男性から紹介された競馬予想サイトに登録して、最初は無料情報でレースに参加していました。ですが思わず有料情報を購入してしまい、そこからは止まれなくなってしまいました。
でもレースには勝てないし、貯金が減っていくので、怪しいと思って調べたところ詐欺だとわかったんです。返金してもらえた今、石田先生には本当に感謝です。ありがとうございます。
この事例ではまず、「最初は無料情報でレースに参加していた」という行動自体が問題です。
一度、ある事柄にたとえ小さな形であっても関わる(コミットする)と、その後の行動にも一貫性を持たせようとする心理が働きます。
無料であっても「参加する」というステップを踏んだことで、被害者は無意識のうちに自分を「このサイトの利用者」と認識し始め、次のステップである有料情報の購入に対する心理的なハードルが自然と下がってしまうのです。
これは、小さな要求から徐々に大きな要求を通す「フット・イン・ザ・ドア」という心理テクニックの応用です。
そして、被害者が購入へと踏み切った背景には、詐欺師によって巧みに醸成された「未来への期待感」と「機会損失への恐怖」があります。
無料参加の期間中、サイト運営者は他の(多くは捏造された)高額な的中実績を見せつけたり、「もうすぐ非常に確度の高いレースがある」といったメッセージを送り続けたりします。
これにより、被害者は「もうすぐ自分も成功できるかもしれない」という強い期待感を抱きます。
同時に、「今、この有料プランに参加しなければその大きなチャンスを逃してしまう」という、得られたはずの利益を失うことへの恐怖心を煽り、冷静に考える時間を与えずに決断を迫るのです。

この事例は、直接的な成功体験という餌がなくとも、小さな関与から始まる「一貫性の原理」と、「未来への期待」そして「機会損失への恐怖」を組み合わせることで、人を高額な支払いへと導くことができる、という詐欺手口の巧妙さを示しています。
「競馬AI資産運用」に潜む騙されるための3つの危険なキーワード
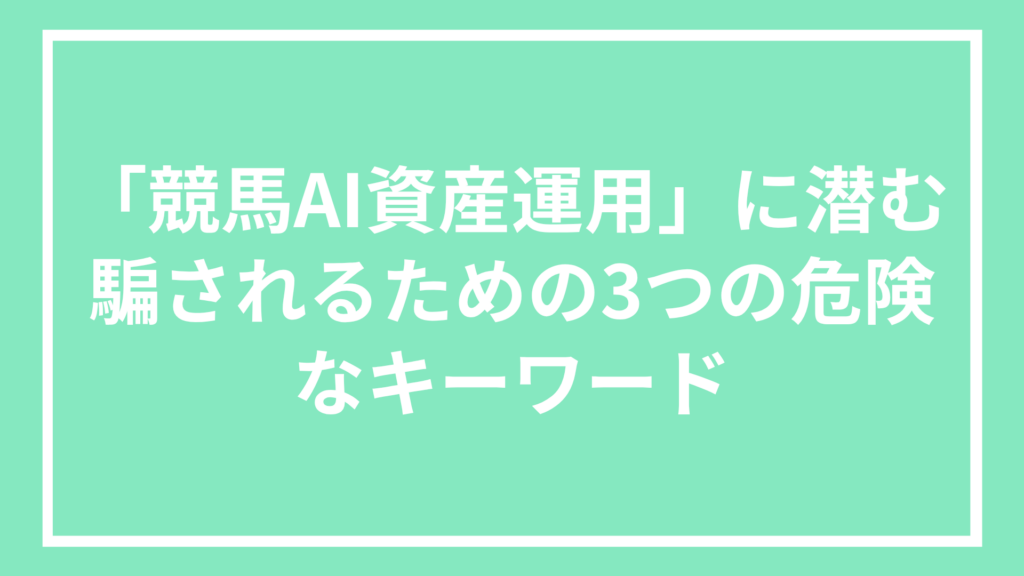
詐欺師は、私たちの願望や心理的な弱みにつけ込むのが非常に巧みです。
特に「競馬AI資産運用」という詐欺被害では、以下の3つのキーワードが悪用されます。
「資産運用」「投資」
詐欺師が用いる最も強力な手口が、この言葉のすり替えです。
社会的に「ギャンブル」という言葉には、どこか不健全、浪費、依存といったネガティブなイメージがつきまといます。
一方で、「投資」や「資産運用」は、計画的、知的、そして将来のための賢明な活動というポジティブな印象を持たれています。
詐欺師は、このイメージの差を巧みに利用します。
競馬は、JRAの収益(控除率約25%)が先に差し引かれ、残ったパイを参加者同士で奪い合う構造上、参加者全体で見れば必ずマイナスになる、紛れもない「ギャンブル」です。
しかし、これを「投資」と言い換えることで、被害者は「自分はリスクの高い賭け事をしているのではなく、未来のために資産を形成しているのだ」と、自身の行動を無意識のうちに正当化してしまいます。
この自己正当化こそが罠の核心です。
罪悪感が薄れることで、高額な情報料を支払うことへの心理的な抵抗感がなくなり、「これは浪費ではなく、リターンを得るための必要経費だ」と、冷静な損得勘定ができない状態に陥ってしまうのです。
「AI」「限定情報」
「最新AIが算出した鉄板の買い目」「元関係者からの極秘情報」といった言葉は、その予想に科学的・客観的な根拠があるかのように見せかけるための演出です。
現代社会においてAIという言葉は、「人間を超えた、客観的で正確無比な分析」という漠然としたイメージを持たれており、多くの人はその言葉だけで思考停止に陥りがちです。
「最新AIが、過去数十年分の全レースデータを解析して導き出した予測」などと言われれば、あたかもそこに絶対的な根拠があるかのように聞こえます。
しかし、そのAIがどのようなアルゴリズムで、何を学習し、その予測精度が本当に高いのかを、利用者が検証することは一切不可能です。
詐欺師は、この「検証不可能性」を逆手に取り、AIというブラックボックスを、中身のない権威として利用しているのです。
さらに、「会員だけの限定情報」「元関係者からの極秘情報」といった言葉は、被害者に「自分はその他大勢とは違う、特別な存在だ」という優越感を与えます。
この「自分だけが特別な機会を得た」という感覚は、情報の価値を不当に高く見積もらせ、高額な料金を支払う判断を後押ししてしまいます。
「初心者でも簡単」「絶対稼げる」
副業を探している人や競馬の知識がない人ほど、このような言葉に惹かれがちです。
現在の収入や生活に不安や不満を抱え、「楽をしてでも現状を変えたい」と願う人々の焦りや一発逆転願望に、「初心者でも」「簡単」「知識不要」という言葉は非常に効果的に響きます。
難しい勉強や努力が不要であると伝えることで、「これなら自分にもできるかもしれない」と思わせ、行動への最後の心理的な壁を取り払うのです。
また、「絶対」「100%」といった断定的な表現は、公営競技の不確実性とは明らかに矛盾しており、それ自体が詐欺的な誇大広告の証拠とも言えます。
これらの言葉は、被害者に「何もしなくても成功できる」という強烈な幻想を抱かせ、冷静なリスク評価を完全に忘れさせてしまいます。
そして、その幻想に引きずられるように、最後の一歩を踏み出させてしまうのです。
しかし、何の努力もリスクもなく安定的に大金が手に入る、などという「うまい話」は存在しません。
これは、あなたの「楽して稼ぎたい」という気持ちにつけ込むための、最も分かりやすい危険信号です。
競馬投資詐欺が返金できないと考える理由
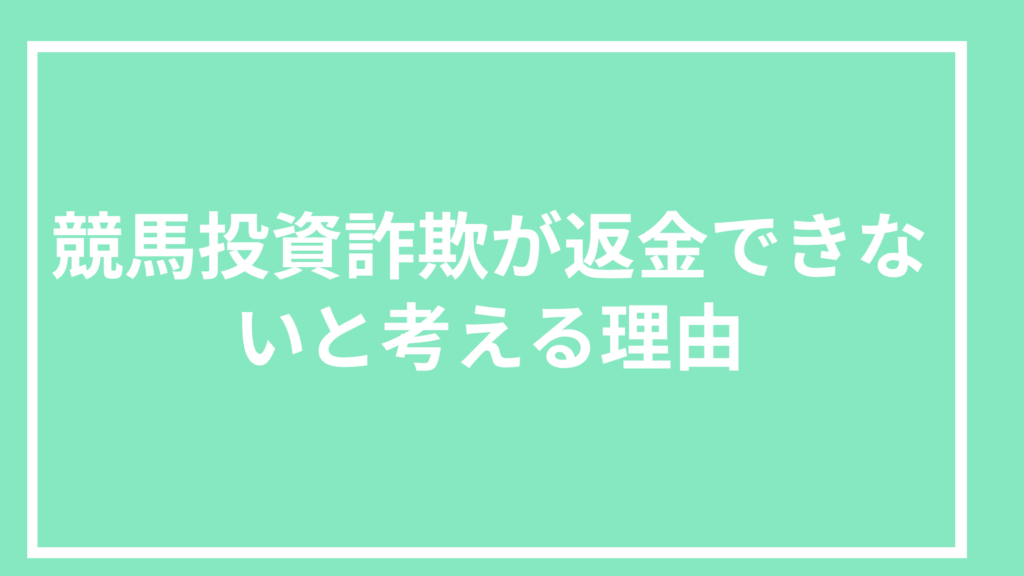
競馬投資詐欺の被害に遭われた方の多くが、「支払ってしまったお金はもう戻ってこない」と、誰にも相談できずに泣き寝入りしてしまっています。
その背景には、詐欺師が巧妙に仕掛けた罠と、法律に関する誤解、そして被害者自身の心理的な障壁が複雑に絡み合っています。
「契約書にサインしたから」という法律的誤解
まず多くの人が返金を諦めてしまう大きな理由に、「契約書にサインしてしまった」という事実があります。
こうした契約書は「特定商取引法に基づく法定交付書面」「売買契約書」などの表題があり、事業者名や商品名、日付など契約書として必要な項目がある書類に自署及び押印をしたことから「一度自分の意思で同意したのだから、契約は法的に有効だ」と考えがちです。
しかし、これは大きな誤解です。契約書は、その締結過程や内容が公正であることが大前提であり、法律は不当な契約から消費者を守るための規定をいくつも用意しています。
例えば、相手に騙されて契約した場合は、民法第96条第1項「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」という規定に基づき、契約そのものを取り消すことが可能です。
「絶対に儲かる」といった嘘の説明を信じて契約した場合、その「騙された」という事実を立証できれば、契約の無効を主張し、支払ったお金の返還を求めることができます。
また、消費者契約法は、事業者と消費者の間にある情報格差を埋めるための強力な味方となります。
同法第4条では、事業者が「将来における変動が不確実な事項につき断定的な判断を提供」した場合(断定的判断の提供)や、「消費者の不利益となる事実を故意に告げなかった」場合(不利益事実の不告知)には、消費者はその契約を取り消せると定めています。
競馬という不確実なものに対して「絶対に儲かる」と説明する行為は前者に、高いリスクや手数料について意図的に隠す行為は後者に該当する可能性が極めて高く、契約書にサインがあったとしても、その契約を取り消せる正当な理由となり得るのです。
「クーリング・オフ期間が過ぎたから」という法律的誤解
次に、多くの人が返金を諦めてしまう大きな誤解として、「クーリング・オフ期間の8日間が過ぎてしまった」というものがあります。
契約の際に「クーリング・オフに関するご案内」といった、赤字などで強調された非常に丁寧な書面を渡してくることがあります。
この書面には、「ご契約から8日以内であれば、書面やメールなどでご連絡いただければ無条件で契約を解除できます」といった内容が詳しく書かれているため、一見すると非常に誠実な対応に見えます。
このように、まるで法律をきちんと守っているかのような丁寧な説明を受けるため、被害者の方は「ちゃんと説明も受けたし、8日が過ぎてしまったのだから、もう返金を求める権利はないんだ」と固く信じ込んでしまいがちです。
しかし、これも返金を諦める理由にはなりません。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘から消費者を守るための特別な制度(特定商取引法第9条など)です。
そもそも、自らサイトにアクセスして申し込むような「通信販売」には、法律上のクーリング・オフ制度は原則として適用されません。
そして最も重要なことは、クーリング・オフは数ある解決策の一つに過ぎないという点です。
たとえクーリング・オフの対象外であったり、期間が過ぎていたりしても、先ほど述べた民法や消費者契約法に基づく「契約の取消権」は、クーリング・オフとは全く別の法的権利です。
これらの取消権は、多くの場合「騙されたと気づいた時から一定期間」行使することが可能であり、「契約から8日間」という短い期間に縛られるものではありません。
「8日間」という広く知られた知識が、かえって他の有効な法的手段があることを見えなくしてしまっているのです。
行動を妨げるその他の心理的障壁
こうした法律に関する誤解に加え、被害者自身の心理も行動を妨げる大きな原因となります。
「楽して稼ごうとした自分が悪い」という強い自責の念や、「結局はギャンブルで損しただけだ」という諦め、そして家族や知人に知られたくないという羞恥心が、誰にも相談できない状況を生み出し、被害者を孤立させてしまいます。
このように、「返金できない」と考える理由のほとんどは、法律に関する誤解や、詐欺師によって植え付けられた思い込みに過ぎません。
泣き寝入りしてしまう前に、まずは一度、詐欺被害に詳しい法律の専門家に相談し、ご自身のケースにどのような法的手段が適用できるのかを客観的に判断してもらうことが、解決への最も重要な第一歩となるのです。
泣き寝入りしないための「返金請求」
「騙された自分が悪い…」「支払ってしまったお金はもう戻ってこない…」
もし被害に遭ってしまっても、そのように自分を責めたり、諦めたりする必要はありません。
先の事例で紹介した3名の方々は、ライトストーン法務事務所に相談することで、支払ってしまったお金の一部、あるいは大部分を取り戻すことに成功しています。
相手方の行為が、詐欺や消費者契約法違反といった違法なものであれば、支払った情報料などを取り戻せる可能性は十分にあるのです。
重要なのは、泣き寝入りせずに行動を起こすことです。
競馬AI詐欺の被害金を取り戻すにはライトストーン法務事務所への相談が解決への近道
では、具体的にお金を取り戻すにはどうすれば良いのでしょうか。
警察や消費生活センターも相談窓口にはなりますが、それらの機関は犯人の捜査やアドバイスが主な役割であり、お金を取り戻すための直接的な返金交渉を行ってくれるわけではありません。
実際に相手方の業者と交渉し、返金を実現するためには、この分野に特化した法律の専門家の力が不可欠です。
中でも、2000件以上の解決実績を持つライトストーン法務事務所は、詐欺被害の返金請求を専門的に取り扱い、豊富な解決実績を持つ司法書士事務所です。
あなたの状況を丁寧にヒアリングし、証拠をもとに、返金の可能性があるかどうか、そしてどのように進めていくべきかを的確に判断してくれます。
「法律事務所への相談は初めてで不安…」という方もご安心ください。
事例の方々のように、勇気を出して相談することが、平穏な日常を取り戻すための最も確実な一歩となります。
一人で悩み続けている間にも、相手の業者が逃げてしまったり、証拠が消えてしまったりと、時間とともに返金の可能性は低くなっていきます。
大切なお金を取り戻すため、まずは一度、ライトストーン法務事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

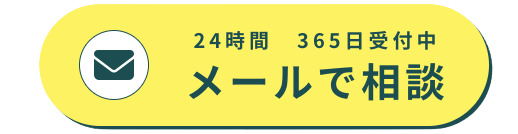
下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)